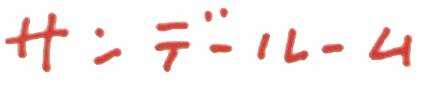サンデールームの創業メンバーはわたしと妹の2人、すぐに末妹も加わり3人で営んでいました。沖縄での学生生活を卒業した妹が私が料理修行を終えて、この先また別の店で働くか実家の店を手伝うかを考えていた時で、「街の中にわたしが行きたいカフェがない」とシャッター街なまちなか、昭和40年代からほぼ変わらない店構え(と言っては申し訳ありません!)が、その変わらなさは伝統でも未来へ続ける意思が感じられず、人が遠のいていくような街に私たちが行く場所、遊ぶ場所、生活の拠点となるような場所を作りたかったのだと思います。
後に、パリのカフェには芸術家が集まっただけでなく、フランス革命も関係したという話も聞き、何かが生まれる場所、創造の場所を作りたった。開店当初は子どもが放課後に秘密基地を作るようなあの感じで、遊びだけれど本気で大真面目だっとのも妹と始めたことも大きいかもしれません。遊びだけれど超本気、この感覚は25年過ぎた今も続いています。さて、行きたい店を作りたいと言っても掲げるビジョンはなく、ただ降りてきたワード「毎日食べられる体にやさしいお昼ごはん」がうっすらとした軸。後のサンデールームに大きく影響することになります。
わたしが食事を作る担当、妹が焼き菓子を作るのとサービスで2人でランチタイムを切り盛りしていました。数年後、末妹が就職先の愛知県から戻り、スタッフが増えたことでお惣菜やお弁当などテイクアウトの充実させ、イベントも増えました。というのも、作業から手が離れると新しいプランが湧き上がってきてしまうというわたしの性分。実家で昔から作り続けてきたおはぎをお盆、お彼岸に販売したり、同じく子どもの時から食卓にのぼっていた調味料をサンデールームのオリジナルの加工品として販売しようと加工場をお借りして作っていただいたり、友人の作家のうつわの展示会、服の展示会を頻繁に開催しました。イベントごとは人がたくさん集まって賑やかでわいわい楽しくはありましたが、わたしたちが大切にしたいのはいつもの日常。「毎日でも食べられる体にやさしいお昼ごはん」をまかない日記や料理教室、日曜市というオーガニックマーケットを開催して、お客様へどのように伝えられるかをいつも考えていました。キッチンで料理を作って食べていただくだけでは何か伝わるものが違う。「美味しかった」「ここでの食事を食べると身体がリセットされる」ありがたい言葉をいただいても何か足りない。私は決して料理の腕があるわけでもない。田畑や農家さんを尊重し、そこからわけていただいた食材に自分の色をつけずに身体の中へ入れることだけを考えて料理をしています。それは自然界からのエネルギーにあれこれ加えずじゃましない、心を込めたり思いを入れずにそのまま通すような食事。ご自身や家族、大切な人に作ったら、または学校給食や病院の食事でも、毎日食べるものはこういうものがよくて、この食事をしていると病気とか悩みとか、生きていて起きうる大変なことをよい感じで乗り越えられるのではないかという漠然とした思いがありました。どうすればこれが伝わるだろう?